



放課後の神無月学園で、一人の少女と対峙する小太郎、誠人、智弘。
学園に異変をもたらしている『鏡のおまじない』。その術式の中心にいた少女は、白滝まどか──術式の首謀者である彼女は、なぜと問う言葉にもうつむいたまま。「あなたにはわからない」――小さくも暗い呟きが、夜の校舎に反響し、鏡が夜の海のように波打つ。夕暮れの校舎に凛と張りつめた危機感が満ち、小太郎はとっさに、鏡へと退魔の札を投げつけた。水のように集う霊力は吹き散らされ、核を失った術式は、呆気なくも崩壊を迎えた。
しかしその崩壊の中、終わりを拒むように鏡へと触れたまどかの手を、腕を体を捕える術式の残滓。鏡へと引きずり込もうとするそれに、彼女は抗うこともせず、鏡の中、別の次元へと消えてしまう。
そして、その一瞬の出来事。まどかが次元の亀裂に飲み込まれる寸前、彼女に向けて伸ばされた誠人の手に、黒い霞のようなものが絡みついたが――それは誰にも気づかれることなく、消え失せた。
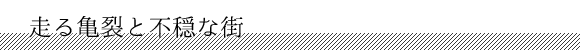
夕暮れの街を落間が駆ける。真面目に霊能業に精を出していたというのに、些細なことで依頼人が逆上、争いになった末、警察沙汰にまでなったのだ。警官を撒いて、ビルの影で一息つく落間。見上げた空は変わらず高いが、彼は何故か、言いしれぬ不安を感じていた。
通りかかった中庭にて、失ってしまった大切な幼馴染──まどかの名に顔を上げた古橋。先輩諸氏の噂話の輪に、怖じ気もなく飛び込む彼。後輩の必死な表情にいぶかしみながらも、その先輩は「夜の校舎で、まどからしき人影を見た」そう語った。その話に何か決意したように走り去る古橋の背中を、同じく話に加わっていた一人、坂本裕子が見つめていた。
同時刻、小太郎達三人は、神楽千歳から鏡に映る霊の除霊を頼まれていた。いざ行ってみれば、鏡の中で動けなくなっていたのは、おぼろげに姿を映すしか力のない、弱弱しい浮遊霊。退魔札を貼り付けただけで退魔は成功したが、『鏡』が関わっていたことが引っ掛かる小太郎。
その違和感を話し合っていた三人だが、誠人のふとした一言に、小太郎は妙な苛立ちを覚え、刺々しい態度で言い返してしまう。言い合ううちに普段の冷静さを失った彼は、誠人に次々と過去の不満をぶちまけた。最後には慌てる誠人を突き飛ばし、去って行く小太郎。立ち上がることも忘れて呆然とした誠人と、状況に追いつけず困惑する智弘。
ひとまず誠人に手を貸そうとする智弘だが、通りかかった生徒に邪魔だと因縁をつけられてしまう。相手が親しいクラスメイトと気づいた誠人が声をかけるも、普段の彼とは全く別人のように、智弘を小突く手は止まらない。たまたま通りかかった智弘の従姉、大上仁子が割って入り、その場は何とか収まったものの、奇妙な違和感が拭い去れなかった。
その違和感をどけるように、大げさなほどに智弘を心配する大上と、視線を逸らし面倒そうに応える智弘。幼少時からの付き合いだという二人を見つめながら、誠人は昔の小太郎と自分の関係を思い出していた。
一方の小太郎は、『鏡のおまじない』事件の依頼人でもある、旧校舎の怪異・影を尋ねていた。
そこで影が告げたのは、『鏡のおまじない』の発動は阻止されたが、完全に消えていないという事実。校舎内の鏡に描かれた印を消し、残る結界を解除しない限り、学園と霊界の繋がりは歪められたままなのだ。糸口を見つけた小太郎は、昼休みの終了を予告する鐘の音の中、結界の解除を約束し、影のもとを後にする。
放課後、一人帰路についた誠人は、反対方向から歩いてくる小太郎を目にする。気づかず通り過ぎていく小太郎が、学園に向かっていることを察し、誠人は智弘に連絡を入れた。「コタちゃんについていってあげて欲しい」後輩に頼み、公園のベンチへと座り込む誠人。そこは昔、幼馴染みとよく遊びに来ていた公園だった。懐かしい遊具を眺めながら、誠人は記憶の糸を辿る。一緒に親の帰りを待ったこと、霊を祓って貰ったこと。どれも、昨日のことのように思い出せた。
ふと、智弘を心配する大上の姿が浮かぶ。兄のようにいた小太郎から見れば、自分は心配の種だった筈だ。霊障で命を落としかけ、小太郎に救われたあの日から、ずっと。小太郎の強さを信じ切って、彼に甘えていた。
ぶちまけられた数々の不満の向こうにいたのは、頼るべき誰かもなく、ただ立ち尽くす少年のような小太郎。その背後に庇われた自分や智弘、もっとたくさんの人々で、彼は転ぶことはない。けれど、握り締められた拳の傷を覆う手も、ない──「強くならないと」。少年の呟きと、夕日に照らされた街を見下ろす誠人の呟きが異なる響きで重なる。大切な幼馴染みに頼るばかりでなく、辛いときには、頼って貰えるように。
――明日になったら、ちゃんと話をしよう。そう決めた誠人の背後に、陽炎のような闇が揺らめいた。

忍び込んだ夜の学園で鉢合わせた古橋と落間、そして坂本。彼らは暗い廊下の先に、走り去るまどかの姿を見かけ、その後を追い走り出す。
一方、智弘と校舎内を探索する小太郎は、廊下で見覚えのある兎の人形を拾い上げた。そこへ走り寄ってきたのは、落としたピーちゃんを探しに来た神楽。手渡されたピーちゃんを抱え、帰ろうとする彼女を見送る為に、昇降口へ向かう彼らだが――扉が、開かない。
扉を押し引きする小太郎達のもとへ、古橋、落間、坂本の三人が駆け込んできた。彼らはまどかを追いかけていたが、ここでその姿が透け、消えてしまったのだという。話し声を聞きつけて現れた大上も、まどかの行方を知ることはなかった。
開かない扉を前に、小太郎が憶測を口にするより早く、何者かの笑い声が降る。「役者が揃ったね?」振り返った先、階段をゆっくりと下りてくるのは、薄ら笑いを浮かべる誠人の姿。――だが小太郎は、直感的に悟った。これは自分の幼馴染みでは無いと。誰何の声に、案の定彼は肩を竦め、『マコト』と名乗った。
──きみたちが殺し合いをすれば、最後の一人は出してあげる──
マコトの要求に、最初に怒りを爆発させたのは落間だった。何を言っている、ふざけるな──怒声を上げ、マコトへ詰め寄る。
しかし、その拳が届く前に、校舎に落ちる影から伸びた黒い触手が、落間の身体を貫いた。それでも尚振り上げられる拳と、射貫くようにマコトを見据える瞳もそのままに、彼の姿が闇に沈む。「殺さなけりゃ、皆殺し」その言葉を残し、マコトは闇と共に虚空へ溶けた。
消えた落間の名を呼び、廊下の奥へ駆け出す古橋を、傍に居た智弘が追う。少し遅れて坂本が続き、大上もまた、そちらへと向かった。
呆然と立ちつくす小太郎を、神楽の声が現実へと引き戻す。我に返った彼は、神楽の手を引き、歩き出した。まずは結界を消さなくては。努めて冷静に考える彼の片手、握り締めた拳が震えていることには、本人さえも気づかなかった。
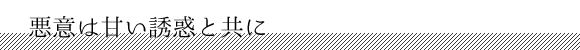
禍々しい気配が渦巻く地下室に、何かが揺らめいている。怒り、憎しみ、絶望――それら全てを内包する純粋な『悪意』の中に浮かぶそれは、肥大化した霊道であった。あまりにも巨大なそれは、霊界の気配すらこの地下室へと近づけている。
それを見つめるマコトの背に、かすかな声がかかる。「本当に殺し合いをさせるの?」振り向いた彼の視線の先には、不安そうに佇むまどかの姿。自身を呼び覚ました「おまじない」の術者に、マコトは口元を歪めて笑った。それが目的じゃないよ、耳朶へ吐息と共にそう囁き、彼女の黒髪を撫でる。囁き声に耳を澄ますように、まどかは震える瞼を降ろした。
そんな二人──いや、自分の身体とまどかから、誠人は視線を逸らす。鎖に絡みつかれた半透明の彼が見下ろすのは、傷つき意識を失ったままの落間。緩やかに上下する胸を濡らす血は薄いものの、まるで苛立ちに満ちた悪夢を見ているかのように、彼の表情は険しく、不意に洩らされる呻き声は怒りに染まっている。
その怒りに満ちた落間の声に誘われるように、歩み寄るマコト。誠人が彼と落間の間に立ちふさがるも、実体を持たない身体は盾にすらならない。「何をするつもり」問いに答えるわけもなく、マコトは彼を擦り抜け、落間の傍らに屈んだ。
マコトの手が落間に触れれば、その胸元から地下室を覆う霞によく似た靄が溢れ出る。それを掴み、ゆっくりと引きずり出してゆくマコト。苦悶の声を上げのたうつ落間は、必死に呼びかける誠人の声にも応えを返さない。
引きずり出した靄にマコトは愛しげに頬ずりをしてから、まるで小鳥を離すかのように、巨大な口を開けた霊道へと放った。霊道がそれを吸い込んだ瞬間、霊道に繋がる誠人の魂に、悪寒に似た何かが走り抜ける。確かに今、この部屋の空気が、漂う気配が、そして繋がったどこかが、濃度を増した。
満足げなマコトの横で、まどかがよろめく。青ざめ、身体を小さく震わす彼女を、マコトは抱き締めるように支える。なんだか気分が悪くて、と謝るまどかの頬を撫で、恋人同士のように額を触れ合わせた。「少し休もうか」何も気づかない彼女を腕に収めたマコトの足元が、まるで水面のように反射する。作り上げられた鏡へ、ゆっくりと沈んでいく二人。
悪意の渦巻く地下室にはただ、呻き声を上げる落間と、その傍らで自身の霊道を見上げる誠人だけが残された。